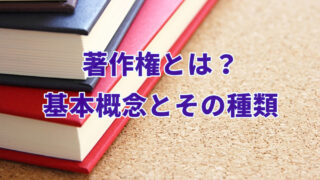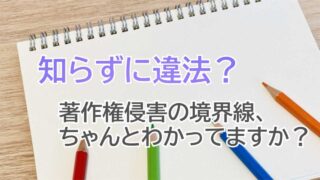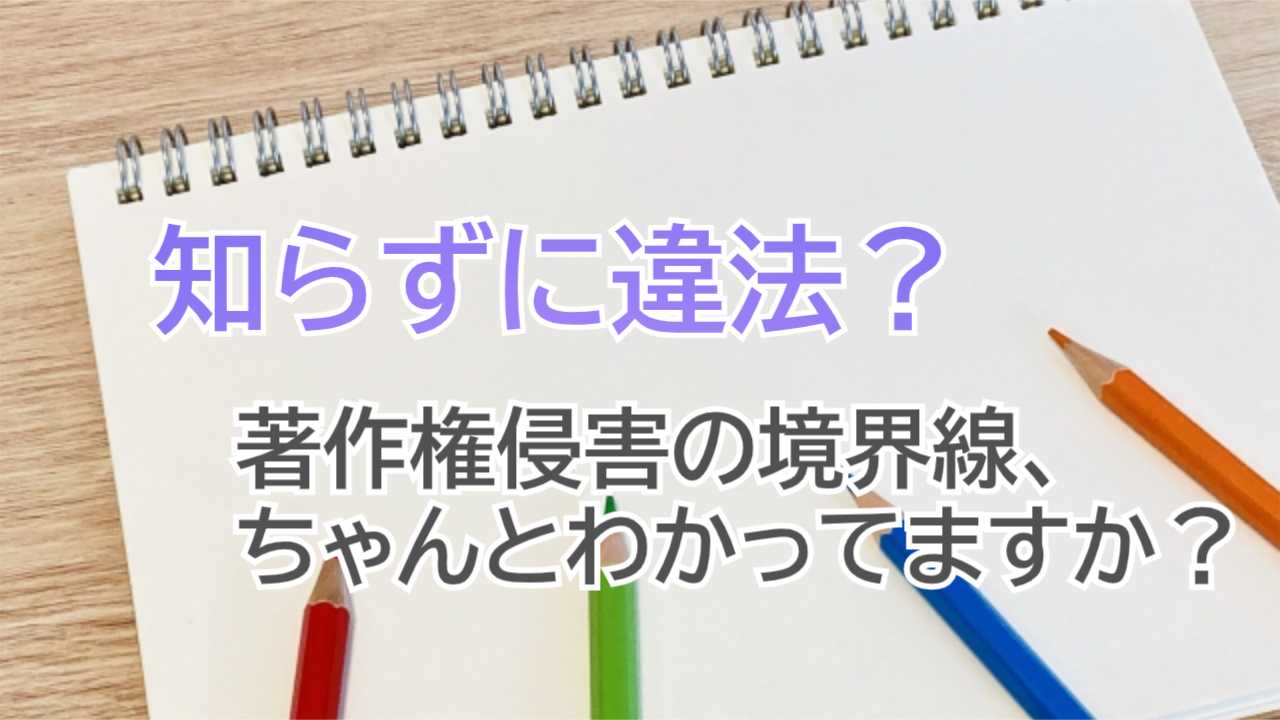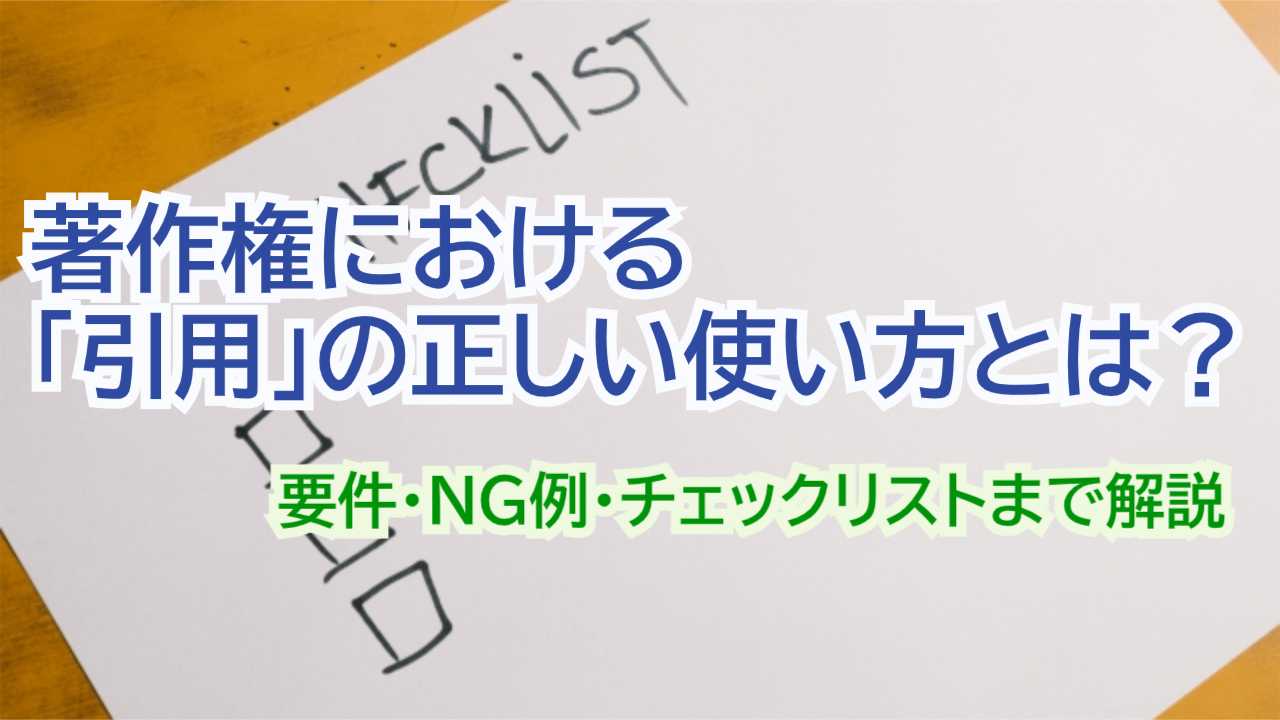「著作権は死後70年まで」──多くの人が一度は耳にしたことのあるルールです。
けれど、この「70年」がすべての著作物にそのまま当てはまるわけではありません。著作者が個人か法人か、あるいは映画作品かによって保護期間は異なり、さらに海外では国ごとに違いがあります。
著作権の保護期間を正しく理解することは、創作者にとっては自分の作品を守るために、利用者にとっては他者の作品を正しく扱うために欠かせません。

この記事を読み終えるころには、「いつまで保護されるのか」「どこから自由に使えるのか」「翻訳や編曲などに新しい権利が発生するケース」まで自信をもって判断できるようになります。
1.著作権の保護期間の基本ルール
著作権は永遠に続くわけではありません。では「いつまで守られるのか?」──その答えを知ることが、この章のテーマです。
ここでは、著作権の保護期間に関する最も重要な原則である「死後70年」ルールについて解説します。
(1)著作者の死後70年(翌年1月1日起算)
著作権の原則は「著作者の死後70年」です。例えば、2020年に小説家が亡くなった場合、その著作物は2090年12月31日まで保護されます。
かつては「死後50年」でしたが、2018年の法改正により「死後70年」に延長されました。この改正は、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)やEU・アメリカとの国際整合性を意識したものです。(参考:文化庁HP)
起算点は「翌年1月1日から」と覚えておくと計算がスムーズです。

2020年12月31日で保護期間が切れます。
- 原則は著作者の死後70年
- 起算点は翌年1月1日から数える
- 2018年の法改正で「死後50年」から「死後70年」へ延長
2.著作権保護期間の「例外」を詳しく解説
著作権の保護期間は原則「死後70年」ですが、実際にはそれだけでは説明できません。法人が著作者となるケースや映画のように多数の著作者が関わるケース、匿名・変名作品などでは特別なルールがあります。
この章では代表的な4つの例外規定を解説します。
(1)法人著作物(職務著作):会社に帰属する場合
企業や団体の業務として作成された作品は、一定の要件を満たすと職務著作(法人著作物)となります。この場合、著作権は社員個人ではなく会社に帰属します。保護期間は公表後70年(翌年1月1日起算)です。未公表の場合は完成後70年です。

(2)映画の著作物:特別な理由で設けられたルール
映画は監督や脚本家や俳優や音楽家など多くの著作者が関わります。もしそれぞれの著作権が別々に計算されると権利関係が複雑になります。そのため映画全体をひとつの著作物として扱う特別ルールがあります。保護期間は公表後70年(翌年1月1日起算)です。未公表なら完成後70年です。
(3)無名・変名著作物:公表後70年が基準
匿名やペンネームで公表された作品は著作者が分からないため、公表後70年(翌年1月1日起算)が保護期間になります。ただし期間中に実名が判明すれば死後70年に切り替わります。
(4)共同著作物:最後に亡くなった著作者が基準
複数の著作者による作品(例:作詞家と作曲家の楽曲)は、最後に死亡した著作者の死後70年(翌年1月1日起算)が保護期間です。共同制作物では誰が最後に亡くなったのかを確認することが重要です。
- 法人著作物(職務著作):公表後70年/未公表は完成後70年
- 映画の著作物:公表後70年/未公表は完成後70年
- 無名・変名著作物:公表後70年/実名判明なら死後70年に切替
- 共同著作物:最後に亡くなった著作者の死後70年
3.パブリックドメインとは?自由利用できる作品の考え方
「パブリックドメイン」という言葉を聞いたことはありますか?
ニュースやネットで見かけても、具体的にどんな状態を指すのかは意外と知られていません。簡単にいえば、著作権の保護期間が終わり、誰でも自由に使えるようになった作品のことです。
ただし「自由に使える」といっても何もかも無条件ではありません。新しい翻訳やリメイクには別の著作権が生まれるため、利用には注意が必要です。
(1)パブリックドメインになるとできること
パブリックドメイン作品は複製、翻案、上映、公衆送信などあらゆる利用が自由です。出版社は再版でき、映画監督は自由に映像化できます。ウェブに公開したり商用に使うことも問題ありません。
(2)新しい二次的著作物に注意
原作がパブリックドメインでも翻訳や編曲や新しい編集が加わると新しい著作権が生まれます。例えば夏目漱石の『坊っちゃん』は既にパブリックドメインですが、現代語訳や漫画版には著作権が発生します。

(3)日本の著名作家とパブリックドメイン
- 夏目漱石(1916年没)→ 1946年12月31日満了(旧法:死後30年)
- 芥川龍之介(1927年没)→ 1957年12月31日満了(旧法:死後30年)
- 宮沢賢治(1933年没)→ 1963年12月31日満了(旧法:死後30年)
- 太宰治(1948年没)→ 1998年12月31日満了(1971年施行後:死後50年)
- 川端康成(1972年没)→ 2042年12月31日まで保護(2018年改正で死後70年)
※2018年改正は、改正時点で存続していた著作権のみ延長。既に消滅していた著作権は復活しません。(出典:文化庁資料「著作権の保護期間の延長について」)
- 保護期間終了後の作品は誰でも自由に利用可能
- ただし翻訳や編曲など新しい表現には別の著作権が発生
- 夏目漱石や芥川龍之介は既にパブリックドメイン、川端康成は2042年末まで保護
4.著作権と混同しやすい「著作隣接権」
クラシック音楽のように古い曲を使おうとしたとき「もう著作権は切れているから自由に使えるはず」と思った経験はありませんか?
ところが実際には「なぜか利用できない」と言われることがあります。その理由は著作権ではなく著作隣接権にあります。
名前が似ているため混同されやすいのですが、両者は保護対象も権利者も異なります。この章では、著作権と著作隣接権の違いを整理し、利用者が注意すべきポイントを解説します。
(1)著作権と著作隣接権の違い
- 著作権:小説、楽曲、絵画などを創作した著作者に与えられる権利
- 著作隣接権:著作物を世の中に伝える実演家、レコード製作者、放送事業者に与えられる権利
つまり「作品そのものを作った人」と「作品を広める役割を担った人」とで、別々に保護されているのです。
(2)クラシック音楽の誤解
ベートーヴェンやモーツァルトの楽曲はすでにパブリックドメインです。しかし市販CDに収録されている演奏音源には、演奏家やレコード会社の著作隣接権があります。そのため、CD音源を動画やイベントで無断使用すると権利侵害になります。

(3)利用者が注意すべきポイント
動画配信者やイベント主催者は、曲がパブリックドメインかどうかだけでなく、使用する音源や映像に隣接権があるかを確認する必要があります。著作隣接権は演奏や録音が行われた時点から一定期間保護されるため、無断利用すればトラブルにつながります。
- 著作権=創作者に与えられる権利
- 著作隣接権=実演家やレコード製作者など「伝える人」に与えられる権利
- クラシック音楽の曲は自由でも録音音源には隣接権がある
- 動画やイベントで使うときは音源や映像の権利を確認することが重要
5.海外作品の保護期間:ベルヌ条約と国際条約の基本ルール
海外の小説や映画や音楽を日本で利用するとき「日本の死後70年ルールを守れば大丈夫」と思っていませんか。実際には国ごとに保護期間の考え方が異なり、単純に日本のルールだけで判断すると誤解やトラブルの原因になります。この章では国際条約と代表的な事例を整理します。
(1)ベルヌ条約の基本ルール
国際的に著作物を扱う際の基本はベルヌ条約です。内国民待遇(利用国の国民と同様に保護)と、翻訳権・上演権などの最低基準を定めます。
この内国民待遇により、外国の著作物も日本の著作物と同様に日本の法律が適用されます。ただし、例外として短期保護の原則があり、外国の著作物の本国における保護期間が日本の保護期間よりも短い場合は、その本国の期間が適用されます。
同じ作品でも利用する国によって保護期間の扱いが変わる可能性がある、という点を押さえておきましょう。
(2)各国比較ではなく「条約」で押さえる:著作権・著作隣接権の主要条約
国ごとの保護年数は改正で変わることがあり、一覧はすぐ陳腐化します。
そこで、この章では各国の制度をつなぐ基盤=国際条約を押さえます。条約を知っておくと、海外作品を日本で使うときの考え方がブレません。
- ベルヌ条約(Berne Convention)
著作権の国際的な基本条約。内国民待遇(利用国の国民と同様に保護)と、翻訳権・上演権などの最低基準を定めます。日本はこの原則に基づき、外国著作物にも日本法の保護を与えます。
また、日本は短期保護の原則(rule of the shorter term)を採用し、本国の保護期間が日本より短い場合は、その短い期間を上限に扱います。 - 万国著作権条約(UCC)
ベルヌ未加盟国との橋渡しとして機能してきた条約。現在は多くの国がベルヌ加盟のため役割は縮小しましたが、歴史的経緯として知っておくと整理しやすい条約です。 - WIPO著作権条約(WCT)
デジタル時代の著作権保護を強化する条約。技術的保護手段(DRM)回避の禁止や、オンライン伝達(公衆送信)に関する権利の明確化など、インターネット環境での保護を補強します。 - WIPO実演・レコード条約(WPPT)
実演家・レコード製作者など著作隣接権の国際保護を定めます。配信時代の実演・録音の権利処理(配信、ストリーミング、再送信など)に関係します。 - TRIPS協定(WTO)
知的財産の最低保護水準と執行を定める国際協定。民事救済や国境措置など、各国に実効的な権利保護・侵害対策を求めます。国際ビジネスでは執行面の基準として重要です。 - ローマ条約(実演家・レコード製作者・放送機関の保護)
伝統的な隣接権の国際保護の枠組み。WPPTの前身的役割を理解するうえで参照されます。
(3)ディズニーと「ミッキーマウス保護法」
アメリカではウォルト・ディズニー社のロビー活動により、著作権の保護期間が繰り返し延長されてきました。俗に「ミッキーマウス保護法」と呼ばれます。2024年には1928年の短編映画に登場する最初期のミッキーマウスがパブリックドメイン入りしました。

- 国際条約を理解することで海外作品利用の基本が見えてくる
- 内国民待遇により外国作品も日本法で保護される
- 短期保護の原則を採用する日本では、本国の保護期間が短ければそれが上限
- デジタル時代の対応はWCT・WPPTが補強、執行面はTRIPSが基準
- ディズニーの事例は「保護延長とパブリックドメインの境界」を考える好例
- 海外作品は最終的に利用国の法律で判断されるため、必ず現行法を確認する
6.判例的トピックとトラブルになりやすいポイント
「著作権の保護期間が切れると、すべて自由に使えるのでは?」と思う方も多いでしょう。しかし実際には、保護期間の前後や復元作業などで新たな権利が発生し、トラブルになることがあります。
この章では、実務で混乱しやすい典型的なケースを取り上げます。
(1)満了前後の契約と新版の扱い
著作権の保護期間が終わりに近づくと、出版社や配信事業者は契約の更新や新版の刊行を検討します。満了前に出版された本は権利者の許諾が必要ですが、満了後に同じ作品を新たに出版する場合は自由に利用できます。ただし、注釈や現代語訳を加えた新版は二次的著作物として新たな著作権が生じます。
古典文学の全集や学生向け注釈書では、この「原作はパブリックドメインだが注釈部分には著作権がある」という事情がしばしば問題になります。

(2)復元・修復・リマスターと権利の所在
古い映画や音楽を復元・修復・リマスターすると、新たな創作性が認められる場合があります。その場合は修復版に新しい著作権が発生します。また、演奏や録音を新たに行えば著作隣接権が生まれます。

(3)美術作品の複製と編集
美術作品の複製もトラブルの原因になりやすい領域です。原作がパブリックドメインでも、新しい写真撮影や色調補正には著作権が認められる可能性があります。特に美術館や出版社が刊行する画集では「撮影者の権利」や「編集上の工夫」が争点になります。
(4)過去の事例から学ぶ教訓
過去には、著作権が切れた作家の全集刊行をめぐって出版社間で争いが起きたケースや、音楽の復刻盤をめぐって隣接権の有無が議論されたケースがあります。これらは「パブリックドメインだから自由」と安易に考えることが危険であることを示しています。
- 満了前後は契約更新や新版の権利を整理しておく必要がある
- パブリックドメインでも注釈や翻訳があれば新しい著作権が発生
- 映画や音楽の修復・リマスターには新しい権利が生じることがある
- 美術作品の複製写真や編集にも権利が認められる可能性がある
- 「自由利用」と思っても新しい表現や行為には注意が必要
7.保護期間の調べ方と実務ツール
「この作品はもう自由に使えるのかな?」と思っても、著作権の保護期間を正しく調べるのは簡単ではありません。著作者の没年や公表年を確認し、場合によっては管理団体や裁定制度を利用する必要があります。この章では、ジャンル別の調べ方と実務で役立つ仕組みを紹介します。
(1)文学作品の調べ方
文学作品の場合は著作者の没年を確認するのが基本です。国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」や作家別の年譜が参考になります。全集や学術書の巻末に没年が記載されていることも多いので、まずは信頼できる資料を確認しましょう。
(2)音楽作品の調べ方
楽曲は作詞者や作曲者の没年を調べることが大切です。日本ではJASRACなどの著作権管理団体がデータベースを公開しており、楽曲タイトルやアーティスト名から権利状況を検索できます。演奏や録音には著作隣接権があるため、音源利用には追加の確認が必要です。
(3)美術作品・写真の調べ方
美術や写真は制作者の没年を調べます。美術館の公式情報や作品カタログ、図録などが手がかりになります。近年の作品は作者が存命であることも多いため、展示や出版の際は直接確認するのが確実です。
(4)権利者不明作品と文化庁の裁定制度
著作者や権利者が不明な場合、そのまま利用すると侵害になる可能性があります。このような場合に備えて、日本には文化庁の裁定制度があります。権利者に連絡できないとき、文化庁長官の裁定を得ることで、一定の条件のもとで合法的に利用できる制度です。

- 文学は著作者の没年を調べる
- 音楽は管理団体のデータベースを活用、音源は隣接権も確認
- 美術や写真は公式資料や図録を参照する
- 権利者不明作品は文化庁の裁定制度で合法的に利用可能
8.まとめ 保護期間を理解して安心して使おう
ここまで著作権の保護期間について、基本ルールから例外、さらにパブリックドメインや国際的な違いまで解説してきました。保護期間は一見単純に見えますが、実際には多くの例外や実務上の注意点があります。
原則は著作者の死後70年ですが、法人著作物や映画は公表後70年が基準です。無名・変名著作物や共同著作物も特別な計算方法があります。期間が終わればパブリックドメインに入り自由に利用できますが、翻訳や注釈、リマスターなどには新しい権利が発生する可能性があります。
また、海外作品を使う場合はベルヌ条約と各国のルールを確認する必要があります。日本では短期保護の原則があるため、本国の保護期間が短ければそれが適用されますが、国ごとにルールが異なるため油断は禁物です。
著作権の保護期間を正しく理解すれば、自分の作品を守りながら他人の作品を安心して活用できます。創作者も利用者もトラブルを避けるために、基礎知識を常にアップデートしておきましょう。
- 原則は死後70年(法人や映画は公表後70年)
- 例外規定(無名・変名、共同著作物)も要チェック
- パブリックドメインでも翻訳やリマスターに新しい権利が発生する
- 海外作品はベルヌ条約と各国ルールを確認する
- 正しい知識があれば安心して創作・利用できる