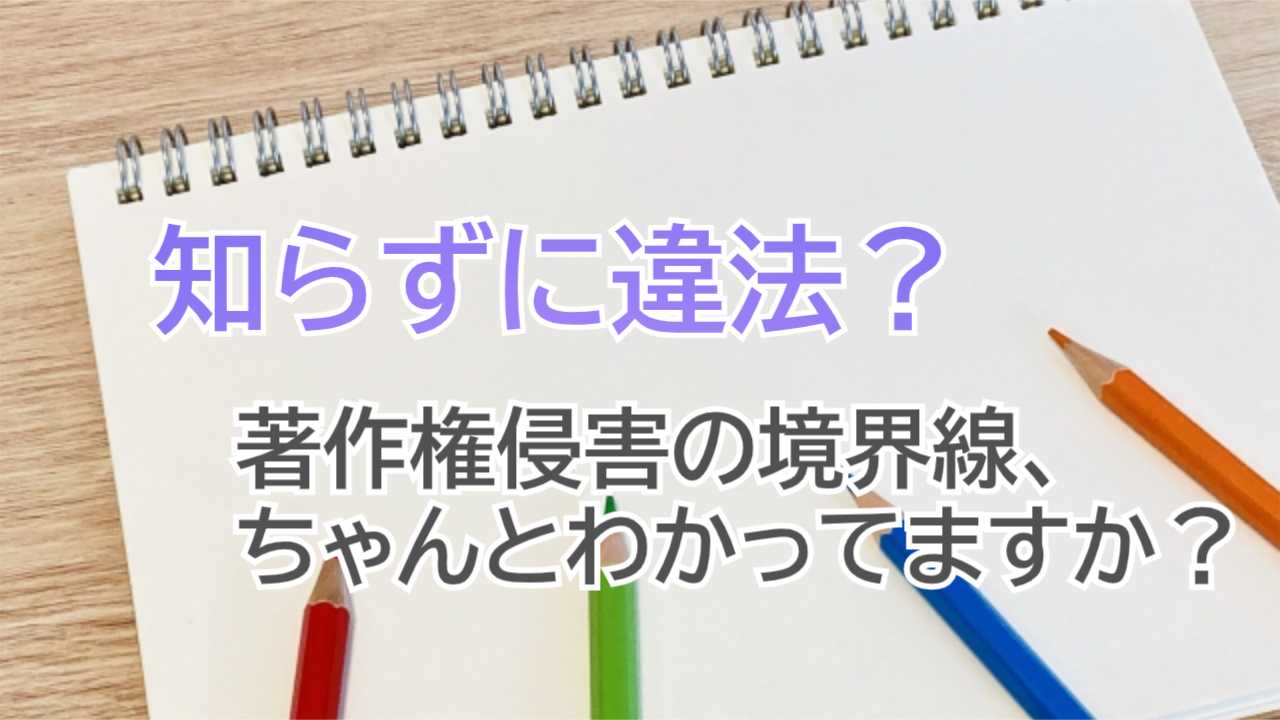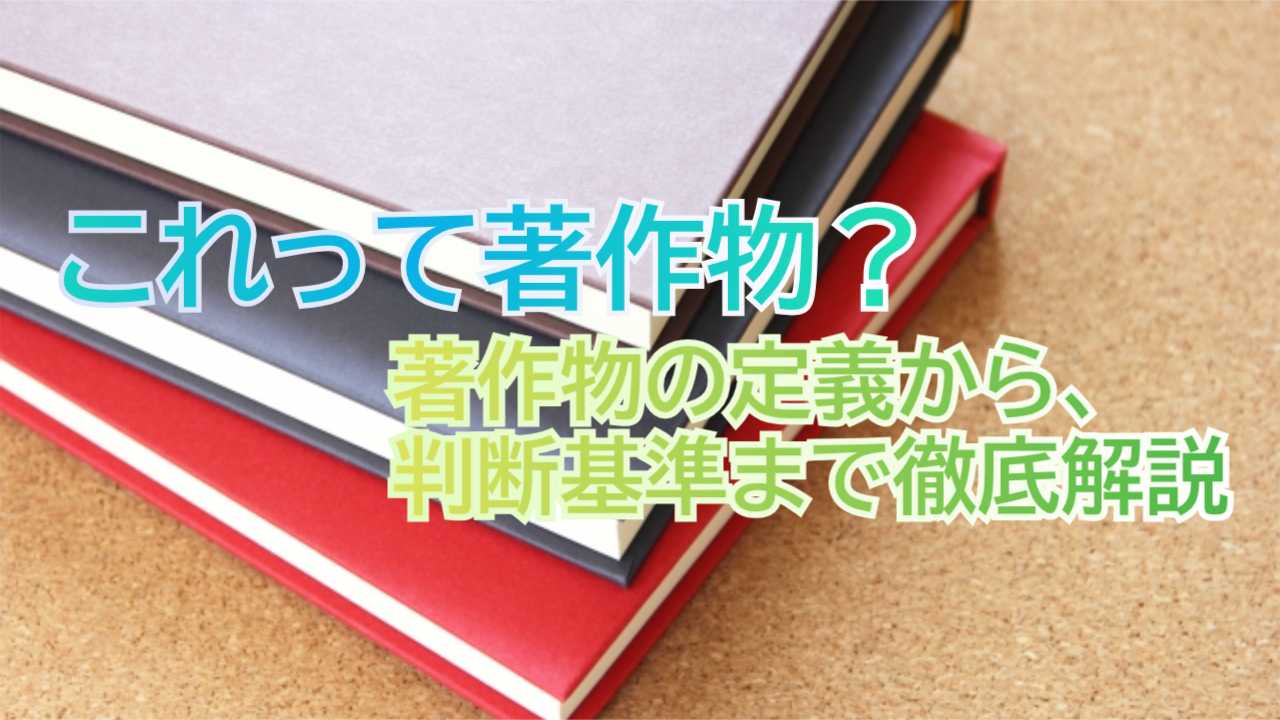「著作権侵害」という言葉はよくニュースやSNSで見かけますが、具体的にどのような行為が違法なのか、どこまでが合法なのかを正確に理解している人は少ないかもしれません。
しかしインターネットやSNSが発達した今、誰でも簡単に画像や音楽、文章をシェアできる時代です。知らず知らずのうちに著作権を侵害し、思わぬトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
この記事では、著作権の基本的な仕組みから、著作権侵害にあたる具体的な事例、そして違法と合法のボーダーラインや対策まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
これを読むことで、安心してコンテンツを作り発信するために必要な知識が身につきます。
1. 著作権とはそもそも何か?
著作権とは、創作した人(著作者)の権利を守るための法律上の仕組みです。
日本では「著作権法」によって、音楽や文章、写真、動画、ソフトウェアなど、人間の思想や感情を創作的に表現したもの(著作物)が保護されています。
著作権が守るもの
- 小説・エッセイ・ブログ記事などの文章
- イラスト・漫画・写真・絵画
- 音楽(楽曲・歌詞・演奏)
- 映画・動画コンテンツ
- コンピュータプログラムやゲーム

例えばYouTubeで動画を公開すれば、その動画は自動的に著作物として保護されます。
特別な登録手続きは不要なんだ。つまり「作った瞬間から守られる」のが著作権の特徴だよ。
著作権の主な権利
著作権は「財産権」と「著作者人格権」に分けられます。
- 複製権:著作物をコピーする権利
- 公衆送信権:インターネットなどで公開する権利
- 翻案権:原作を脚本や映画に作り変える権利
- 氏名表示権・同一性保持権:著作者として名前を表示する権利や、勝手に改変されない権利
これらの権利を持つ著作者は、許可なく利用された場合には利用停止を求めたり、損害賠償を請求することができます。
2.著作権侵害とは?定義とポイント
著作権侵害とは、著作権者が持つ権利を、許可なく他人が侵害する行為を指します。
例えば、無断で著作物をコピーしたり、インターネットにアップロードする行為がこれにあたります。
日本の著作権法では以下のような権利が保護されており、それを勝手に行使することが侵害になります。
- 著作物をコピーする「複製権」
- インターネットで公開する「公衆送信権」
- 翻訳や脚色などを行う「翻案権」
「引用」との違い
よく「これは引用だから大丈夫」と言う人がいますが、引用は著作権法で厳格な要件が決められています。
- 引用部分が主ではなく、あくまで自分のコンテンツが主体
- 引用部分を明確に区別する(カギカッコや引用タグなど)
- 出典をきちんと明示する

例えばブログで「この映画は最高だった!」と一言書いて、その下にセリフを丸々載せるのは引用にならないよ。
あくまで自分の解説や批評が主体で、引用はそれを補足する形じゃないといけないんだ。
二次創作やSNSのシェアは大丈夫?
二次創作(原作をもとにした漫画や小説など)は、原則として著作権者の「翻案権」を侵害する可能性があります。ただし黙認されているジャンルも多く、ファン活動としてグレーゾーンになりやすいのが実情です。
また、SNSでの「公式のシェアボタンを使う」行為は、多くの場合プラットフォーム利用規約で許諾されており問題ありません。しかしスクリーンショットや画像を無断転載するのはリスクが高いので注意しましょう。
3.著作権侵害のよくある事例
ここまで著作権や著作権侵害の定義について解説してきましたが、具体的にどのような行為が著作権侵害となるのでしょうか?
インターネットやSNSが普及した現代だからこそ起こりやすい、代表的な事例を紹介します。
無断でネット上の画像をブログに使用
Google画像検索などで見つけた写真やイラストを、許可なく自分のブログやSNSに掲載する行為は典型的な著作権侵害です。

「ネットに載ってる=自由に使っていい」って誤解してる人が多いけど、実際はほとんどが著作権で守られているから要注意だよ!
YouTubeやTikTokで音楽を勝手に使う
J-POPやアニメソングをBGMとして使った動画を、著作権者の許可なく、または動画配信サービスが提供する公式音源ライブラリなどを利用せずに投稿すると、音楽の著作権(公衆送信権や演奏権)を侵害します。
最近は自動検出システムで削除・収益化停止されるケースも多く、JASRACから警告が届く場合もあります。
SNSで漫画や雑誌の記事を無断転載
雑誌や漫画のページをスマホで撮影して、そのままSNSにアップする行為も複製権・公衆送信権の侵害です。
特にフォロワーが多いアカウントほど出版社から削除要請が来やすくなります。
社内資料に雑誌記事を無断コピー
研修用の資料に雑誌記事をコピーして配布する行為も、本来は著作権者の許可が必要です。
営利目的でなくても関係なく、企業の内部資料だから大丈夫という誤解がよくあります。
4.著作権侵害が発覚した場合のリスク
著作権侵害が発覚すると、思いがけない大きな責任を負うことになります。
個人ブログや趣味のSNS投稿であっても「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされません。
差止請求・損害賠償請求
著作権者は著作権法に基づき、無断利用している人に対して
- コンテンツの掲載停止(差止請求)
- 使用料相当額や逸失利益の賠償(損害賠償請求)
を求めることができます。
刑事罰
著作権侵害は刑事罰の対象にもなります。
著作権法第119条では、
「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」
(法人の場合は3億円以下の罰金)という非常に重い罰則が規定されています。

実際には和解や削除で済むことが多いけど、悪質だと訴訟になるケースもあるよ。
企業が絡むと信用問題になって大きな損失を被ることもあるから注意してね。
社会的信用の失墜
著作権問題はネットニュースやSNSで大きく拡散されることがあります。
「〇〇社が著作権侵害」と報じられれば、ユーザーや取引先からの信頼を一気に失うリスクがあります。
5.著作権侵害を防ぐためにできること
ここまで読んで「ちょっと怖くなった」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、ポイントを押さえれば安心してブログやSNSを運営できます。
著作権侵害を防ぐための基本的な対策を紹介します。
フリー素材やライセンスの確認を徹底する
インターネットには「商用利用可」「クレジット不要」と記載されたフリー素材サイトが多くあります。
必ず利用規約を確認し、許可された範囲内で使用しましょう。

「フリー素材だから何に使ってもOK!」って思いがちだけど、再配布禁止や二次利用不可の条件が付いていることも多いから注意してね。
正しい引用を心がける
引用は著作権法で認められていますが、主従関係・引用部分の明示・出典の表示を守ることが大前提です。
曖昧な引用はトラブルのもとになるので、ルールをしっかり守りましょう。
クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスに注意
「CCライセンス」は、著作権者が自分の著作物を第三者に利用してもらう際のルールを、あらかじめ明確にして公開する仕組みです。
ただし、すべて自由に使えるわけではなく、ライセンスの種類によって利用可能な範囲が異なります。
基本の4要素は次のとおりです(出典:https://creativecommons.jp/licenses/)
- BY(表示):クレジット(著作者名)の表示が必要
- NC(非営利):営利目的での利用は禁止
- ND(改変禁止):作品の改変は禁止
- SA(継承):改変した場合も同じライセンスを適用すること
これらを組み合わせて、6種類のライセンスが提供されています:
- CC BY:表示のみ(営利利用・改変・再配布もOK)
- CC BY-SA:表示+継承(改変OK、同じ条件で再配布)
- CC BY-ND:表示+改変禁止(営利利用OKだが改変不可)
- CC BY-NC:表示+非営利(営利利用不可、改変OK)
- CC BY-NC-SA:表示+非営利+継承
- CC BY-NC-ND:表示+非営利+改変禁止(最も制限が厳しい)

「CC BY-NC-ND」は非営利かつ改変禁止だから、企業のサイトで使ったり、画像に文字を入れて加工するのもNG!
フリー素材に見えても、利用条件はしっかり確認してね。
また、ライセンスによっては「改変してはいけない」「クレジット表記が必須」「商用利用はNG」などの条件があります。使用前にライセンスの全文を確認し、必要なら著作者に直接確認をとるのが安心です。
トラブルが起きた場合は専門家に相談
もし「これって著作権侵害になるのかな?」と不安に思ったら、弁護士や専門機関に相談するのがおすすめです。
特に、インターネット上の著作権侵害については文化庁の著作権に関する相談窓口も活用できます。
(参考:文化庁:インターネット上の海賊版対策に関する相談窓口)
6.まとめ
著作権は、クリエイターの権利を守ると同時に、私たちが安心してコンテンツを楽しむために欠かせない重要なルールです。
しかしSNSやブログが当たり前になった今、知らずに侵害してしまうケースが増えています。
この記事で紹介した
- 著作権の基本的な仕組み
- 侵害にあたる具体例
- 違法と合法の境界線
- トラブルを避けるための対策
を参考にして、正しい知識を身につけておきましょう。
そうすることで、あなた自身が安心して発信し、他人の作品をリスペクトしながらインターネットを楽しめるようになります。