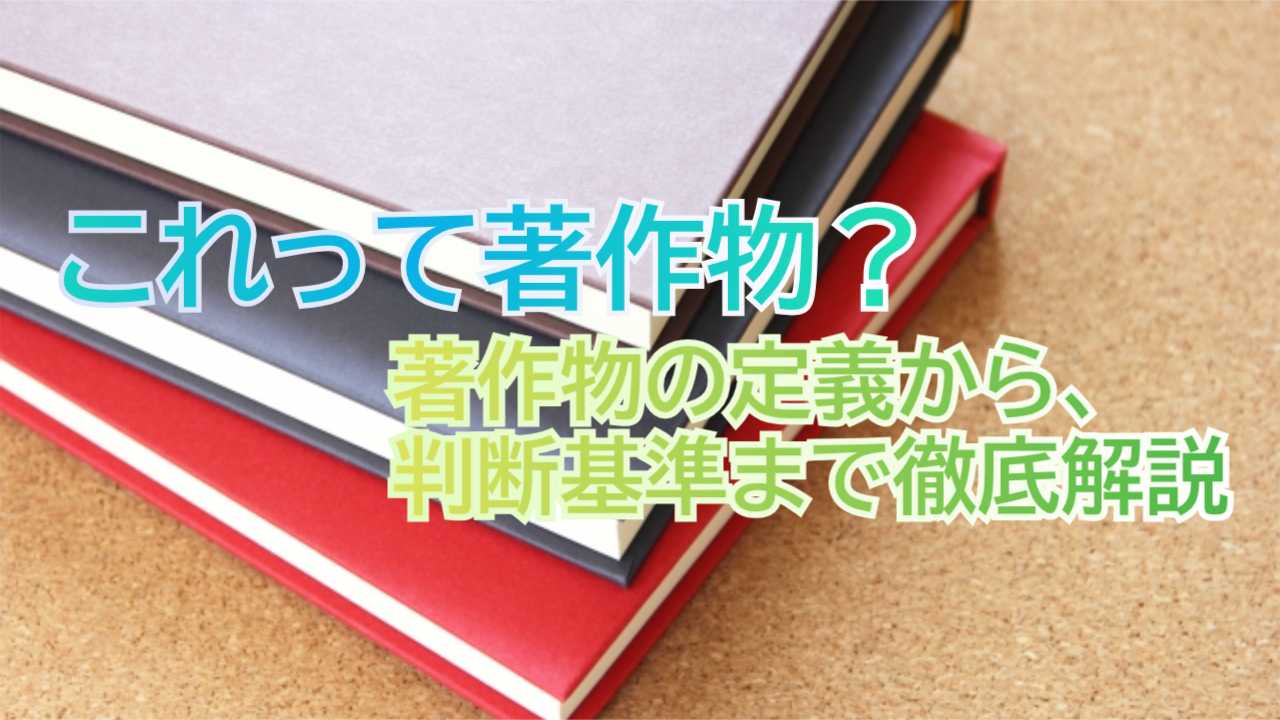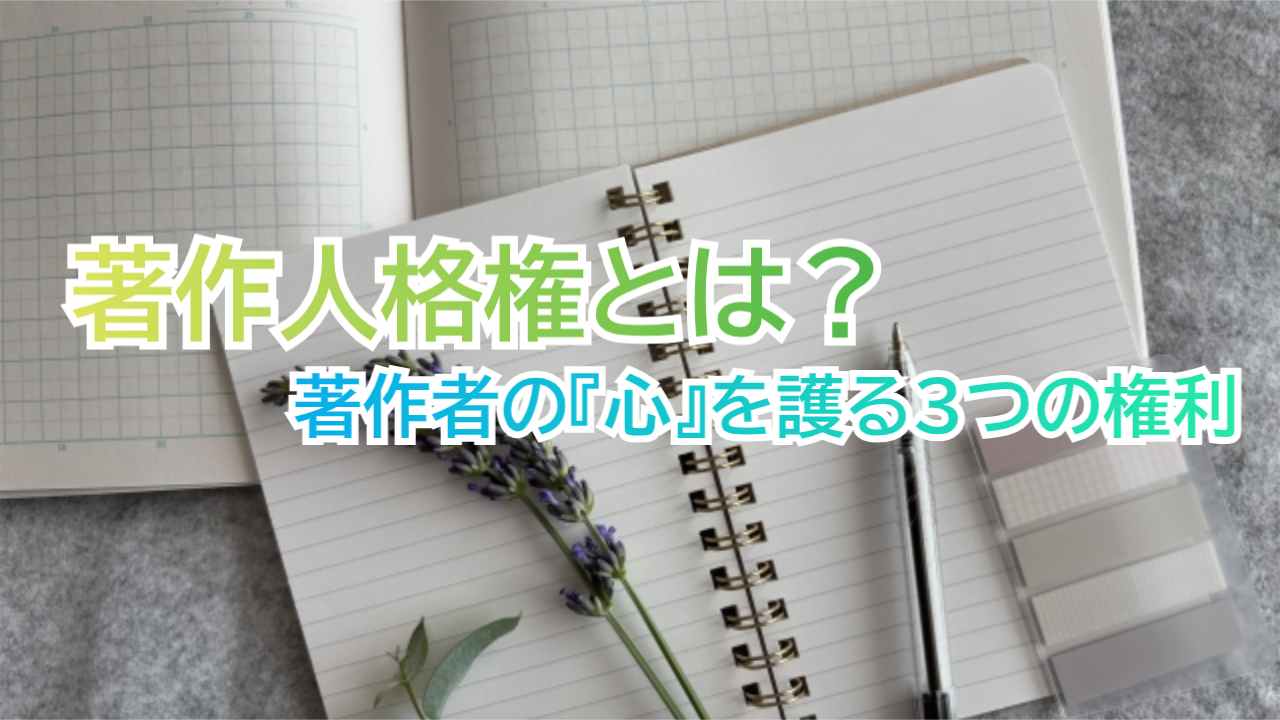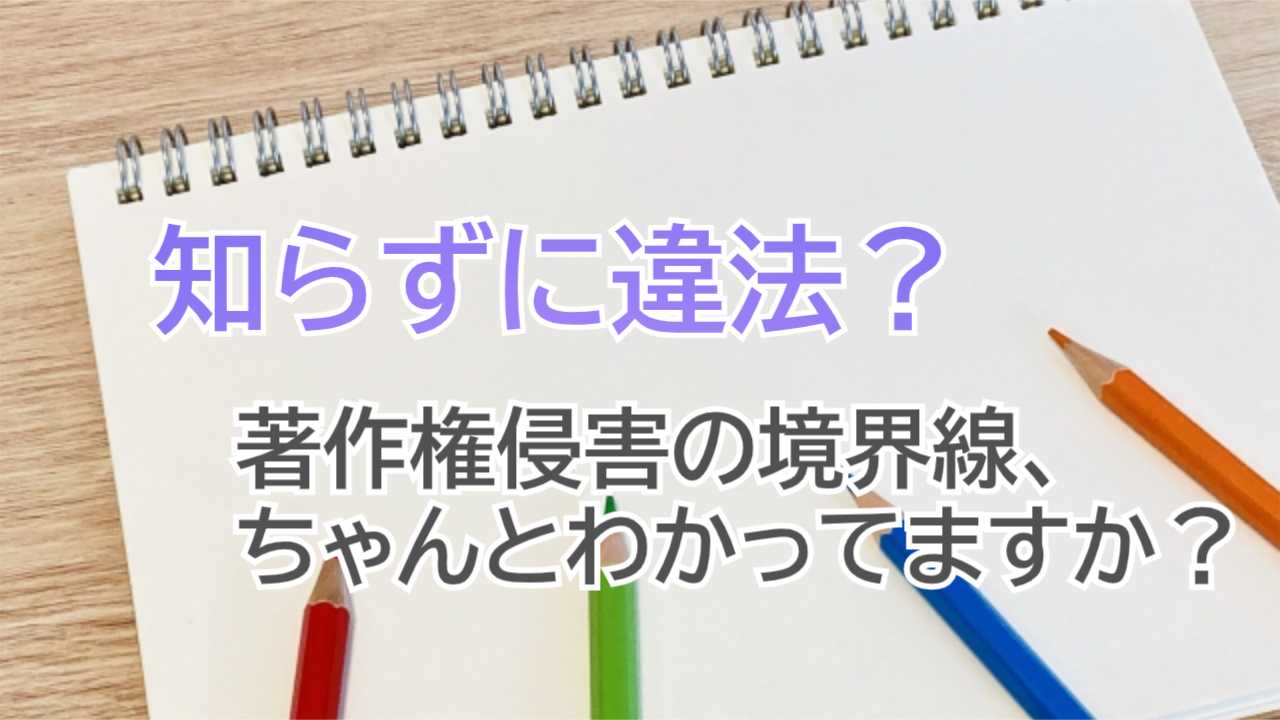「著作物」とは何か、具体的に何が著作権で保護されるのか、疑問に感じたことはありませんか?
小説や音楽といった芸術作品はもちろん、実は日常的に書くブログの記事やSNSに投稿した写真も、あなたの個性や工夫が詰まっていれば「著作物」として保護される可能性があります。同時に、インターネット上にある他者のコンテンツも「著作物」である可能性があり、その利用には注意が必要です。
この記事では、著作権法における「著作物」の定義から、保護されるもの・されないもの、そして判断のポイントを具体例を交えて分かりやすく解説します。
最後まで読むことで、著作物に関する正しい知識が身につき安心して創作・発信活動ができるだけでなく、他者の作品を利用する際のトラブルも避けられるようになるでしょう。
著作権は、クリエイターだけでなく、インターネットで情報収集をしたり、SNSでシェアしたりする私たち全員にとって大切な基礎知識です。ぜひこの記事を参考に、著作権を正しく理解し安心してコンテンツを楽しめるようにしましょう。
1.著作物とは?
まず、著作物がどのように定義されているのかを見ていきましょう。
日本の著作権法では、著作物は次のように定義されています。
著作権法 第2条第1項第1号
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
つまり、単に思いついたアイデアや知識そのものではなく、それを作者が自分なりに表現したものが著作物となります。
ここでは「創作的」「表現」という点がとても大切です。

そのアイデアを、あなたらしく表現して初めて著作物として守られるんだよ。
著作物のポイントは「創作性」と「表現性」
法律の文章だと難しく感じるかもしれませんが、次の2つを満たすかがポイントです。
- 創作性:作者の個性や工夫が反映されていること
- 表現性:具体的な形(文章、音、画像、動画など)で表されていること
例えば、単なる「富士山が美しい」という考え(アイデア)は誰のものでもありません。
しかし、これをあなたの言葉で詩にしたり、絵に描いたり、写真で撮影した場合は、その具体的な形が著作物として保護されます。
アイデアやデータは著作物じゃない
この「アイデア自体は著作権では保護されない」という点は、著作権の基本中の基本です。
例えば、料理のレシピの「こういう材料を使って作る」というアイデア自体は自由に使えます。
ただし、それを文章で細かく解説したり、動画で作り方をわかりやすく見せたりすれば、その表現部分が著作物になります。
このように、著作物とは単なる思いつきやデータの羅列ではなく、作者の創意工夫が込められ、具体的に表現されたものを指すのです。
2. 著作権で保護される具体的な著作物の例
著作物の定義がわかったところで、次は実際にどのようなものが著作権で保護されるのか、具体的な例を見ていきましょう。
言語の著作物
- 小説、エッセイ、詩
- ブログ記事やWebコンテンツ
- 学術論文、評論
- 脚本、シナリオ、講演
インターネット上に公開した文章も、基本的には著作物として保護されます。

音楽の著作物
- 楽曲(メロディ・ハーモニー・リズム)
- 歌詞
- ラジオドラマ、ポッドキャストの脚本や台本
ちなみに楽譜だけでも著作物ですが、それを演奏した音源はまた別の権利(著作隣接権)で保護されます。
美術の著作物
- 絵画、イラスト、漫画
- 彫刻、版画、書道
- デザイン性のあるロゴや商品パッケージ
美的鑑賞の対象となるものが該当します。
映画の著作物
- プロが撮影した写真はもちろん、スマホで撮ったオリジナル写真も
- 映画、アニメ、YouTube動画
写真は撮影者の「構図やタイミングの選択」に創作性が認められるので、著作物になりやすいです。
建築の著作物
- デザイン性のある建築物(例: 著名な建造物や個性的な家屋)
ただし機能性のみを追求した一般的な設計図などは著作物と認められにくい場合があります。
図形の著作物
- 地図
- 学術的な図面、図表
- イラスト調の案内図
図形によって表現されたものが該当します。ただし地形データそのものや単純なグラフは保護の対象外になることがあります。
プログラムの著作物
- ソフトウェアのプログラム(ソースコード)
ソフトウェアプログラムも著作権法上「著作物」として保護されます。
独自のアルゴリズムやアイデアは保護されませんが、それを具体的にコードとして表現した部分は著作権が及びます。

舞踊、無言劇の著作物
- 舞台での演技、振付
- 講演、スピーチの原稿
身体の動きや表情によって表現されたものが該当します。
3.保護されないものの例
著作権法は「思想や感情を創作的に表現したもの」を保護します。
そのため、逆に以下のようなものは著作権で保護されないとされています。
単なるアイデアや思いつき
「こんな漫画の設定を思いついた」「こういうアプリを作ったら面白そう」といったアイデアそのものは、著作権法では保護されません。
これは著作権法第2条で明確に「表現されたもの」でなければならないとされているためです。

でも、そこから具体的な小説を書いたらその文章表現は著作権で守られるよ。
単なるデータや事実
- 統計データや事実の羅列
- 単純なリストや表(例:都道府県名の一覧)
これらは「事実そのもの」なので、著作権の保護対象外です。
ただし、そのデータを見せ方に工夫してデザインや解説を加えた場合は、その表現部分が保護されることがあります。
短すぎる表現
極めて短いタイトルやキャッチコピー、単語やスローガンなどは、通常「創作性がある表現」とまでは認められにくいです。
ただし、短いフレーズであっても独創性が非常に高い場合には、稀に保護対象になることがあります。
法律や判決文、行政文書
日本では、法令・判決・行政の告示などは国民の共有財産として自由に利用できます(著作権法第13条)。
このため、法律条文や裁判所の判決文をそのまま引用することは問題ありません。
公共の場所に恒久設置された建築物や彫刻の撮影
街中に設置されている銅像やモニュメントを写真に撮る行為は、「著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)」により認められています。これは、公共の場所に恒久的に設置された美術の著作物や建築の著作物は、原則として自由に利用できるという規定です。
ただし、美術館や私有地の中にある作品を撮影する場合は別のルールが適用されるので注意しましょう。

でも、美術館の中の作品は施設の規則もあるし著作権上も注意が必要だよ。
ただし、別の法律(商標法や不正競争防止法など)で問題になるケースもあるため注意しましょう。
4.著作物と認められるかどうかの判断ポイント
ここまでで、著作物は「思想や感情を創作的に表現したもの」であると説明してきました。
では、あなたが作った文章やイラスト、写真は著作物として認められるのでしょうか?
ここでは著作物かどうかを判断するための代表的なポイントを紹介します。
(1)独自性があるか(誰が作っても同じにならないか)
著作物として保護されるためには、作者の個性が表れていることが重要です。
例えば、単純に「表を作って数字を並べただけ」や「定型的なフォーマットに従って書かれた報告書」は、独自性が低いため著作物と認められにくい場合があります。
(2)創作性があるか(どこかに工夫やオリジナリティがあるか)
多少なりとも作者の工夫や感性が反映されていれば、著作物として認められるハードルはそれほど高くありません。
例えば短い文章であっても、詩的で独創的な表現であれば著作物となります。

ちょっとした個性や言葉選びがあれば、それはもう立派な著作物だよ。
(3)表現されているか(アイデアの段階で止まっていないか)
著作権は「表現」を保護するので、頭の中のアイデアだけではダメです。
文章にしたり、絵に描いたり、音にして録音するなど、具体的な形でアウトプットされてはじめて保護されます。
(4)自然や物理法則に従うだけのものではないか
例えば、単に「太陽が東から昇る様子をそのまま撮影しただけ」の動画は、誰が撮影しても同じになりやすいため創作性が認められないケースもあります。
しかし、撮影アングルや演出にこだわれば著作物となる可能性があります。
◎結局、少しでも作者のセンスや個性が感じられるかどうか
このように一見難しそうな著作物の判断基準ですが、少しでもあなた自身の感性や個性が表れていれば、それは立派に著作権で保護される対象です。
安心して、あなたらしい表現を大切にしてください。
5.よくある質問Q&A
Q. SNSに投稿した写真も著作物になるの?
はい、スマホで撮影した写真であっても、撮影者の構図やタイミングの選択などに創作性があれば、立派な著作物として著作権法で保護されます。

「ネットに出ているから自由に使える」とは限らないんだ。
Q. AIが作った画像は著作物になる?
現行の日本の著作権法では、著作物は「人間の思想や感情を創作的に表現したもの」とされています。このため、原則としてAIが自律的に生成した画像は著作物とは認められません。
ただしAIの利用過程で人間が具体的な構図や内容を細かく指示・調整するなど、その指示や調整に創作性が認められる場合には、人間の著作物と認められる可能性について議論がされています。この分野は現在も活発に議論されており、今後の法改正や解釈の動向に注目が集まります。
Q. 友達が描いたイラストを自分のブログに載せてもいい?
基本的にNGです。著作物は作者(著作者)が権利を持っており無断で利用することは著作権侵害となります。
掲載したい場合は必ず描いた本人に許可を取りましょう。

Q. 引用はどうなの?
著作権法では「引用」が認められており、一定のルールを守れば他人の著作物を使うことができます。
引用のポイントは以下です。
- 引用部分が主ではなく、あくまで自分の文章が主体
- 引用部分を明確に区別し、出典を表示する
これを守らないと引用ではなく「無断転載」になり、著作権侵害になる可能性があるので注意しましょう。
6.まとめ
この記事では、著作権法における「著作物」の定義から、著作権で保護されるもの・保護されないもの、そして著作物かどうか判断するポイントについて具体的に解説してきました。
- 著作物とは「思想や感情を創作的に表現したもの」
- 小説、音楽、イラスト、写真、プログラムなど多様なものが著作物になる
- 単なるアイデアやデータは保護されない
- 少しでも個性や工夫があれば、それはあなたの著作物
著作権について正しく理解しておくことで、無用なトラブルを避けられるだけでなくあなた自身の創作物をしっかり守ることにもつながります。

これからも楽しく創作や発信を続けてね。
もし自分の作品が著作物として守られるか心配だったり、他人の著作物を使う際に不安があるときは専門家に相談するのも一つの方法です。
著作権を正しく理解し、あなたらしい表現活動を存分に楽しんでください。