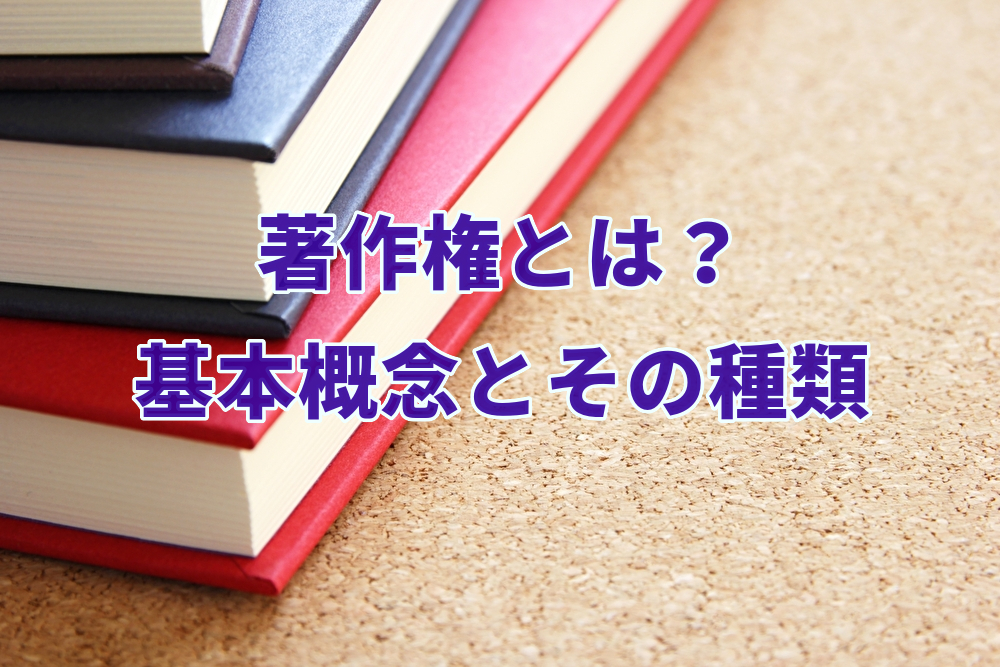「著作権」という言葉を耳にすることは多いけれど、「具体的に何を守るためのもの?」「自分の作ったものにも著作権ってあるの?」「どこまでなら使ってもOKで、どこからがNGなんだろう?」――そんな疑問を感じたことはありませんか?
著作権とは、音楽や本、映画など、様々な作品を作った人の権利を守るためのルールです。 この記事では、著作権の基本を分かりやすく解説し、皆さんの日常生活や仕事で著作権を適切に扱うための知識を深めていただければ幸いです。
1.著作権とは?
(1)著作権の定義
そもそも著作権とはどういった権利なんでしょうか。
著作権とは、ある人が作った作品(著作物)に対して、その人が持つ特別な権利のことです。例えば、音楽を作った人は、その音楽をどう使うかを決める権利があります。この権利は、作品が作られた時点で自動的に発生し、特別な手続きをしなくても有効です。つまり、あなたが自分で書いた詩や撮った写真にも、自然と著作権がつくということです。

学生時代にノートの切れ端にこっそり書いたイラストにも著作権は発生するんだね。
(2)著作物とは何か
前段ではある人が作った作品に対して著作権が発生すると説明しました。著作物とは、人の考えや気持ちを創造的に表現したもののことをいいます。
例えば、以下のようなものがあります。
- 小説や詩、エッセイなどの文章
- 音楽や歌詞
- 絵画や彫刻
- 建物のデザイン
- 写真や動画
- コンピュータプログラム
これらは全て、作った瞬間に著作権が発生します。ただし、実際に発生した事実のみを記載した文章などは著作物にはなりません。

「1847年2月11日はトーマス・エジソンの誕生日です。」という文章は事実の記載に過ぎないので著作物にはならないんだ。
(3)著作権の歴史と背景
日本の著作権法は明治32年(1899年)に初めて制定されました。この法律は著作物を作る人の権利を保護し、それによって文化が発展していくことを目指しています。その後、社会のデジタル化や新しい技術の登場に合わせて何度も改正が重ねられてきました。これにより日本の著作権法は現代のニーズに対応し、国際的なルールにも沿う形で整備されています。
2.著作権の種類
著作権には「著作権(財産権)」と「著作人格権」の二つの主要な種類があります。
ここからはそれぞれの具体的な内容をご説明していきます。
(1)著作権(財産権)
著作権(財産権)は、作品を使ってお金を得るための権利です。
著作人格権と異なり、他人への譲渡や相続が可能です。
以下に、著作権(財産権)の具体的な権利を紹介します。
| 権利種別 | 内容 |
|---|---|
| ①複製権 | 作品をコピーする権利 |
| ②上演権・演奏権 | 作品を公に上演・演奏する権利 |
| ③公衆送信権 | インターネットや放送を通じて作品を公衆に伝達する権利 |
| ④口述権 | 作品を読み上げる権利 |
| ⑤展示権 | 美術作品や写真を展示する権利 |
| ⑥頒布権 | 作品のコピーを配る権利 |
| ⑦譲渡権 | 作品の所有権を他人に譲る権利 |
| ⑧貸与権 | 作品を一定期間貸し出す権利 |
| ⑨翻訳権・翻案権 | 作品を他の言語に翻訳したり、別の形態に改作する権利 |
作品をコピーする権利です。
例えば、本を無断でコピーして販売することは複製権の侵害です。
作品を公の場で上演・演奏する権利です。
他者が作成した演劇を無断で上演することは、この権利の侵害になります。
インターネットや放送を通じて作品を公衆に伝達する権利です。
他者が作った音楽を無断でインターネット上で配信することなどはこの権利の侵害に当たります。
作品を読み上げる権利です。
小説の朗読を無断で行うことはこの権利の侵害です。
美術作品や写真を展示する権利です。
他者の絵画を無断で展示することは展示権の侵害に該当します。
映画の著作物や、録音・録画されている著作物の複製物を公衆に提供する権利です。
例えば、映画のコピーを無断で販売することなどがこの権利の侵害に該当します。
映画の著作物や、録音・録画されている著作物の複製物を公衆に譲渡する権利です。
他者の作品の複製物を無断で他人に譲渡することは譲渡権の侵害に当たります。
録音・録画されている著作物の複製物などを公衆に貸し出す権利です。
映画のDVDや音楽CDを無断で貸し出すことなどがこの権利の侵害です。
作品を他の言語に翻訳したり、別の形に改作する権利です。
例えば、小説を無断で他の言語に翻訳することなどがこの権利の侵害に該当します。

お気に入りの映画を勝手にコピーしたり、学祭などで上映したりすることも著作権の侵害に該当するんだ。他者が創作したものは必ず創作者の許可を得て利用することが大切だね。
(2)著作人格権
著作人格権は、著作者の名誉や信用を守るための権利です。以下に、具体的な権利を紹介します。
| 権利種別 | 内容 |
|---|---|
| ①公表権 | 作品を発表するかどうかを決める権利 |
| ②氏名表示権 | 作品に自分の名前を表示するかどうかを決める権利 |
| ③同一性保持権 | 作品の内容を勝手に変更されないようにする権利 |
公表権とは、作品を発表するかどうかを決める権利です。ある作家の未発表作品を無断で公開されると、この権利が侵害されます。
氏名表示権とは、作品に自分の名前を表示するかどうかを決める権利です。作品に表記している自分の名前を無断で消されたり、自分の作品に他人の名前を勝手に使われるなどすると、この権利を侵害したといえます。
同一性保持権とは、作品の内容を勝手に変更されないようにする権利です。例えば、絵画の一部を無断で改変するなどは、この権利の侵害に該当します。

SNSなどで拾ってきた他人のイラストや写真を、自分の作品だと偽ることは著作人格権の侵害に当たるんだ。一部分だけを切り取ってSNSにアップロードすることも著作人格権侵害になるよ。
3.著作権の保護期間
(1)著作者の権利の保護期間
著作権の保護期間は、著作者の生涯とその死後70年間です。これは、著作者が作品を作り続けるためのインセンティブを提供し、死後も遺族がその権利を享受できるようにするためです。
(2)著作隣接権の保護期間
著作隣接権は、著作物を伝達する人(例えば、実演家、レコード制作者、放送事業者、有線放送事業者など)の権利です。これらの権利の保護期間は、以下のようになっています。
- 実演家の権利:実演が行われた時点から70年間
- レコード制作者の権利:レコードが発行された時点から70年間
- 放送事業者の権利:放送が行われた時点から50年間
- 有線放送事業者の権利:有線放送が行われた時点から50年間

青空文庫でなぜ多くの小説が無料で読めるのかというと、この著作権の保護期間が過ぎた作品が多く保管されているからなんだよ。
4.著作権の制限
著作権にはいくつかの制限があり、特定の条件下では著作物を自由に利用することができます。
(1)私的使用のための複製
個人的な目的で著作物をコピーすることは許可されています。自分だけで楽しむために音楽を録音したり、本をコピーすることがこれに該当します。
(2)引用
他人の著作物を引用することは、一定の条件下で許可されています。引用する際には、出典を明示することが求められ、さらに公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われる必要があります。例えば、研究や評論において、他人の作品を一部引用することが認められています。
(3)教育機関における利用
学校などの教育機関では、授業の一環として著作物を利用することが許可されています。教科書の一部をコピーして生徒に配布することなどは認められています。
(4)図書館等における複製
図書館では、保存や研究目的のために著作物をコピーすることが許可されています。例えば、絶版となった書籍の保存や、利用者の研究のためのコピーが含まれます。
(5)福祉目的の複製
福祉目的で著作物をコピーすることも許可されています。視覚障害者向けに書籍を点字に変換することなどが該当します。

著作権によって創作者の権利が守られている一方で、作品の有意義な活用もまた認められているんだね。
5.著作権侵害とその対策
著作財産権や著作人格権の説明でも少し触れた、著作権侵害について解説します。
(1)著作権侵害の定義
著作権侵害とは、著作者の許可なく著作物を使用する行為を指します。これには、無断で複製、配布、改変することが含まれます。
(2)著作権侵害の例
著作権侵害の具体例としては、以下のようなものがあります。
- 音楽や映画の違法ダウンロード
- 書籍の無断コピー
- 他人の作品を改変して公開する行為
(3)著作権侵害への対応方法
著作権侵害が発生した場合、著作者は法的手段を取ることができます。これには、まずは侵害行為をやめるよう警告書を送ったり、話し合い(交渉)をしたりするほか、状況によっては、損害賠償の請求や、侵害行為の差し止めを求める訴訟を提起するといった手段が含まれます。

自分の作品を無断で使われたり、作者だと偽って世間に公開されたときは法的手段を取ることができるんだね。
6.著作権に関する国際条約
(1)ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関する条約)
ベルヌ条約は、著作物の国際的な保護を提供するために制定され、各国の著作物が他国でも保護されることを定めています。
日本は1899年にこの条約に加盟しており、著作権の自動的な発生や外国で作られた著作物も一定の要件を満たせば保護されるといった内容を採用しています。ベルヌ条約の影響で日本の著作物も加盟国で自動的に保護されるという利点があります。
(2)WIPO著作権条約(WCT)
1996年に採択されたWIPO著作権条約(WCT)は、インターネットの普及に対応するための条約で、デジタル化に伴う著作権の新たな課題に取り組む内容が含まれています。日本もこの条約を批准しデジタルコンテンツの保護や配信権の強化を法に取り入れています。これにより、日本の著作権法もデジタル時代に適応する形に更新されています。
(3)TRIPS協定(知的財産権の貿易関連の側面に関する協定)
TRIPS協定は、著作権や特許、商標など知的財産全般に関する包括的なルールを規定しており、WTO(世界貿易機関)加盟国間での最低限の知的財産保護水準を確保する目的があります。日本もWTO加盟国としてこの協定を順守しており、著作権保護期間や権利侵害に対する罰則などについてもTRIPS協定に準じています。
(4)WIPO実演及びレコード条約(WPPT)
WIPO実演及びレコード条約(WPPT)は、実演者とレコード制作者の権利を保護するための条約です。日本はこの条約を批准し、国内法でも実演家やレコード制作者の権利が強化されています。この条約への加入により、音楽などの実演や録音作品も国際的に保護されるようになりました。
(5)マラケシュ条約(視覚障害者等のための著作物利用の促進に関する条約)
マラケシュ条約は、視覚障害者や読字障害者のために著作物の利用を促進することを目的としており、特定の条件のもとで著作物の複製や配布が認められています。日本もこの条約を批准しており、視覚障害者等が著作物にアクセスできるよう支援しています。
7.まとめ
著作権は、作品を作った人の権利を守り、文化の発展を支えるために重要な法律です。著作権の基本を理解することで、日常生活や仕事において適切に著作権を扱えるようになります。著作権の保護期間や制限、侵害への対策など、幅広い知識を身につけて、安心して作品を楽しみましょう。