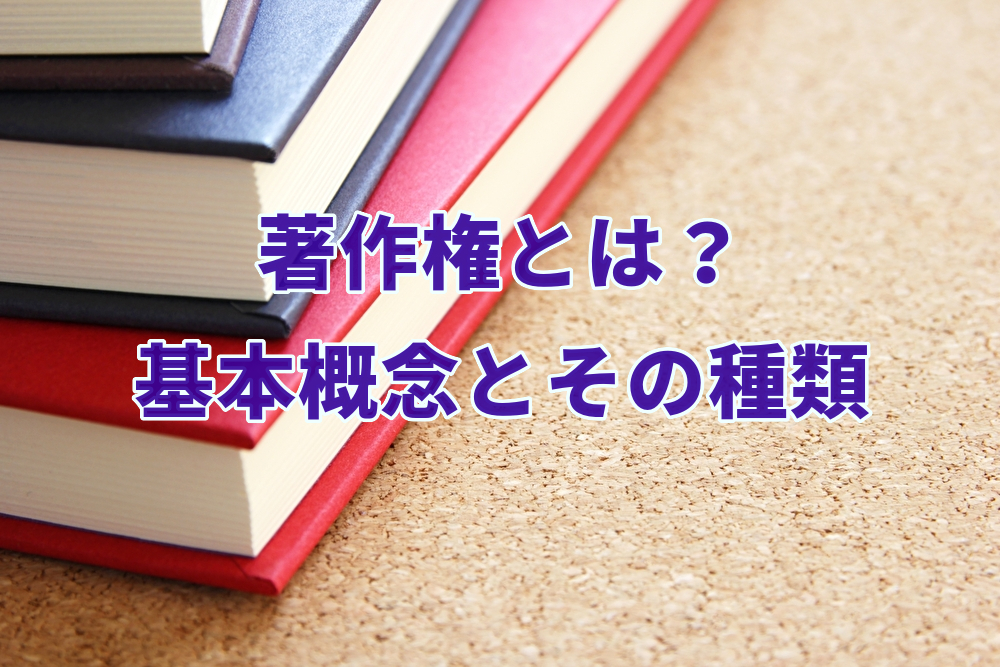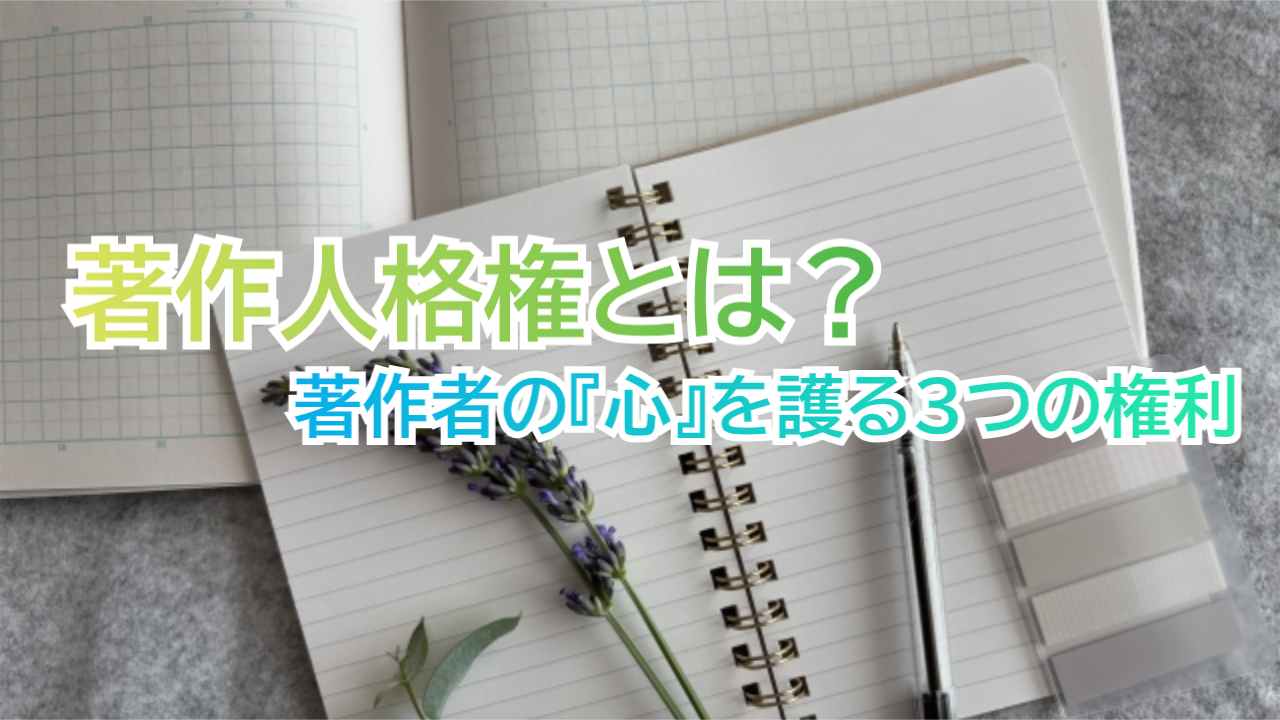著作財産権は、作品を作った人が自分の作品をどう使うかを決める大切な権利です。
この権利を理解することは、作品を守り、正しい方法で利益を得るために必要です。本記事では、著作財産権の基本的な考え方から、具体的な権利内容、使い方や管理方法について解説します。
インターネットの普及により、作品が簡単に共有される一方で、著作権の侵害も増えています。そのため、著作財産権について知っておくことはとても大切です。この記事を読んで、著作財産権についての基礎知識をしっかりと身につけておきましょう。
1.著作財産権の基本概念
(1)著作権と著作財産権の違い
「著作権」という言葉はよく耳にしますが、実は著作権には「著作者人格権」と「著作財産権」の2つが含まれています。
- 著作者人格権:作品が著作者の意図しない形で改変されないようにする権利や、著作者の名前を表示する権利などです。これは譲渡できない、著作者だけの権利です。
- 著作財産権:作品を使ってお金を稼ぐための権利です。たとえば、作品をコピーしたり、インターネットで配信したりする権利が含まれます。こちらは譲渡や相続が可能です。
ここがポイント!「著作権」は2つの権利の総称
「著作権」と一言で言っても、実は「著作者の人格を守る権利(著作者人格権)」と「作品を使ってお金を稼ぐ権利(著作財産権)」の2つが含まれています。特に「著作財産権」は、譲渡や相続が可能なので、ビジネスで作品を扱う際にはこの権利を理解することがとても大切になります。

2020年代には、ジャスティン・ビーバーやKISSといったセレブたちが自身の楽曲を売却したと大きく報じられたけど、これを日本での出来事と置き換えると、著作財産権を譲渡したということになるよ。もちろん、海外と日本では扱い方が異なるからあくまでもイメージとして考えてね。
(2)著作財産権の法的根拠
日本では、著作財産権は「著作権法」で保護されています。この法律は、文化の発展を促進するために、作品を作った人(創作者)の権利を守ることを目的としています。
著作権法は、著作物が創作された時点で自動的に著作財産権が発生すると定めています。つまり、著作物を創作した瞬間から、創作者には著作財産権が認められるのです。
この権利は、特許や商標とは異なり、特別な手続きや申請をしなくても自動的に発生します。これにより、創作者は自分の作品を即座に保護することができます。
重要!著作権は「無方式主義」
日本の著作権法では、著作物が創作された瞬間に自動的に著作権が発生します。これを「無方式主義(むほうしきしゅぎ)」と呼びます。
特許や商標のように、国に申請して登録しなくても、作品が完成した時点から法的に保護されるので、クリエイターは安心して創作活動に専念できます。

著作権って、作品を作ったら自動的に発生するんだ!どこかに申請しに行かなくても、すぐに自分の作品が守られるって安心だね。
保護される著作物の種類
著作財産権で守られる作品は、以下のように多岐にわたります。
- 文学的な作品: 小説、詩、論文など
- 音楽: 作曲、歌詞など
- 映像作品: 映画、テレビ番組、アニメなど
- 美術作品: 絵画、彫刻、写真など
- 建築作品: 建物やその設計図など
- プログラム: コンピュータソフトウェアなど
これらの作品は、無断で使ったりコピーしたりすることができません。著作財産権は、これらの作品を保護し、創作者が正当な報酬を得ることを保証しています。
2.著作財産権の内容と種類
著作財産権には、さまざまな種類の権利があります。ここでは、それぞれの権利を個別に解説します。
(1)複製権
複製権(コピーライト)は、作品をコピーする権利です。この権利は、作品が物理的にコピーされる場合(本をコピーする、CDを複製するなど)や、デジタル形式でコピーされる場合(ファイルをコピーする、インターネットにアップロードするなど)に適用されます。
知ってた?「コピーライト」は和製英語?
よく作品のクレジットなどで見かける「©(コピーライト)」マークですが、これは英語圏で著作権を示す言葉として広く使われています。
しかし、日本の著作権法上の正式名称は「複製権」です。このマークがなくても著作権は保護されますが、著作権表示として一般的に使われています。
- 本の無断コピー:書店で販売されている人気作家の小説を、誰かが無断でコピーしインターネット上で無料配布することは複製権の侵害です。この場合、著者や出版社は法的措置を取って、この違法行為を止めさせることができます。
- デジタルアートのスクリーンショット:アーティストがSNSに投稿した作品のスクリーンショットを取って、他のウェブサイトやSNSで共有することも、複製権の侵害にあたります。アーティストの許可なく行うことは、法的に問題があります。
(2)公衆送信権
公衆送信権(インターネット配信など)は、インターネットやその他の通信手段を通じて、著作物を公衆に送信する権利です。これには、インターネット上でのストリーミングやダウンロードが含まれます。
- 音楽のストリーミングサービス: 音楽ストリーミングサービス(SpotifyやApple Musicなど)で楽曲を配信する場合、サービス提供者はアーティストや音楽会社から公衆送信権の許可を得なければなりません。無許可で楽曲を配信することは、この権利の侵害となります。
- YouTubeでの映像配信: YouTubeで映画やテレビ番組の一部を無断で配信することも、公衆送信権の侵害です。著作権者は、このような違法配信を止めるために、削除要請や法的措置を取ることができます。
(3)上映権
上映権は、映画や映像作品をスクリーンなどで上映する権利です。この権利は、劇場での映画上映だけでなく、学校やイベントでの上映にも適用されます。
- 映画の無断上映: 学校の文化祭で、生徒が人気映画を無断で上映しようとした場合、この行為は上映権の侵害にあたります。映画の上映には、必ず著作権者の許可を得る必要があります。
- 市民ホールでの映像上映: 地元の市民ホールが、有名なドキュメンタリー映画を無断で上映する場合、上映権の侵害となります。このような場合、主催者は映画の著作権者に事前に許可を求めなければなりません。
(4)上演権
上演権は、音楽、演劇、舞踏などの作品を公衆の前で演じる権利です。この権利は、劇場での演劇やコンサートなどに適用されます。
- ミュージカルの無断上演: 地元の劇団が著名なミュージカル作品を無許可で上演する場合、これは上演権の侵害となります。著作権者の許可を得ずに上演することは違法です。
- 音楽コンサートでの無断演奏: ライブハウスで、人気アーティストの楽曲を無断で演奏することも、上演権の侵害に該当します。このような場合、主催者は事前に著作権管理団体から許可を得る必要があります。
(5)口述権
口述権は、著作物を公に朗読する権利です。これは、詩や物語の朗読などに適用されます。
- 詩の朗読会: ある詩人の詩集を使って朗読会を開く場合、その詩の著作者から口述権の許可を得る必要があります。無許可で詩を朗読することは、口述権の侵害になります。
- オーディオブックの朗読: 作家の小説を朗読してオーディオブックとして配信する場合も、著作者の口述権の許可が必要です。許可なく配信すると、権利侵害となります。
(6)展示権
展示権は、美術の著作物や写真の著作物の原作品を、美術館やギャラリーなどの公共の場で公に展示する権利です。これは、絵画や彫刻、写真といった作品を、多くの人の目に触れる形で公開するために必要な権利です。
- 美術館での絵画展示: 有名画家の絵画を美術館で展示する場合、美術館はその画家またはその権利者から展示権の許可を得なければなりません。無断で展示することは、展示権の侵害です。
(7)頒布権
頒布権は、映画や映像作品などを複製して、広く配布する権利です。この権利は、作品を市場に流通させる際に重要です。
- 映画のDVD販売: 映画の製作会社がDVDを作成して販売する場合、頒布権が関係します。無断でコピーしたDVDを販売する行為は、頒布権の侵害です。
- 音楽アルバムの販売: 音楽アルバムのCDを作成して販売する場合、アーティストやレコード会社は頒布権を有します。無断でコピーしたCDを販売することは違法です。
(8)譲渡権
譲渡権は、著作物の原作品やその複製物(コピーされたもの)を、公衆に譲り渡す(販売するなど)権利です。例えば、CDやDVD、書籍などを最初に販売する際にこの権利が関係します。
ただし、一度適法に販売された著作物(例:正規のルートで購入した本やCD)については、その後、個人が中古品として他人に譲り渡したり、中古書店で販売したりする行為は、原則として著作権者の許諾は不要とされています。これを「著作権の消尽」と呼びます。
- CDやDVDの販売:音楽レーベルや映画製作会社が、CDやDVDを製造し、小売店を通じて消費者に販売する行為に譲渡権が関係します。
- 中古CD・DVDの販売:一度正規に購入されたCDやDVDを、中古品として個人がフリマアプリなどで譲渡したり、中古ショップが買い取って再販したりすることは、著作権者の譲渡権を侵害するものではありません。
(9)貸与権
貸与権は、著作物を貸し出す権利です。これには、レンタルショップでの映画やゲームの貸し出しなどが含まれます。
- レンタルショップでの映画貸し出し: 映画のDVDをレンタルショップで貸し出す場合、ショップは製作会社から貸与権の許可を得る必要があります。無断で貸し出すことは、貸与権の侵害にあたります。
- 図書館での本の貸し出し: 図書館で本を貸し出す場合も、貸与権が適用されますが、教育や文化のために特別な例外規定が設けられている場合もあります。

こんなにたくさんの権利があるのは、作品の使い方が多様だからなんだ。どんな使い方をしても、作者の権利が守られるように細かく分かれているんだよ。
3.著作財産権の取得と存続期間
著作財産権の発生要件
著作財産権は、作品が創作された瞬間に自動的に発生します。特別な手続きや申請をしなくても、著作者の権利は守られます。
自動的に発生する権利
著作財産権は、自動的に発生するため、クリエイターは作品の創作に集中でき、発表の瞬間から保護されます。
法定期間とその延長
日本では、著作財産権の保護期間は、原則として著作者の死後70年間です。この期間は、著作者が作品を創作してから亡くなった後も、その著作物が保護され続けることを意味します。
ただし、無名・変名(ペンネームなど)の著作物や、団体名義の著作物、または映画の著作物など、一部の特別な著作物については、保護期間の数え方が異なり、公表後70年と定められています。
著作権法改正と存続期間の変遷
著作権法は時代に応じて改正されており、著作財産権の存続期間もそのたびに見直されています。
保護期間「50年→70年」の背景
著作権の保護期間は、かつては著作者の死後50年でしたが、2018年の著作権法改正により70年に延長されました。
これは、TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)の発効に伴い、国際的な保護期間の基準に合わせたものです。これにより、日本の著作物も海外でより長く保護されるようになりました。

著作権の保護期間って、昔は死後50年だったんだけど、実は最近(2018年)変わって70年になったんだね。国際的なルールに合わせたんだ!
国際的な保護とベルヌ条約
著作財産権は国際的にも保護されており、ベルヌ条約に加盟している国々では、日本の著作物も同様に保護されます。
5. 著作財産権の行使と管理
著作権管理団体の役割
著作財産権の管理は、専門の著作権管理団体によって行われることが多いです。たとえば、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽作品の使用を管理しています。

JASRACってよく聞くけど、私たちの好きな音楽がテレビやお店で流れるのは、こういった団体がちゃんと権利を管理してくれてるおかげなんだね!
著作権契約とライセンスの種類
著作物を使うには、著作権契約やライセンス契約が必要です。これには、独占的に使える契約や複数の人が使える契約があります。
著作権侵害に対する対策
著作財産権が侵害された場合、法的措置をとることができます。差止請求や損害賠償を求めることが可能です。
侵害に対する救済措置
侵害が起きた場合、まずは侵害行為を止めるために差止請求を行い、損害が発生した場合は損害賠償を求めることができます。
著作権者の権利と制限
著作権者には、自分の作品をどう使うかを決める権利がありますが、日本の著作権法では、一定の条件下で、著作権者の許諾なく著作物を利用できる「権利の制限」の規定があります。例えば、私的使用のための複製や、公正な慣行に合致した引用の範囲内であれば、他の人が許可なく著作物を使うことが認められています。
6. 著作財産権の限界と制約
私的使用など、著作権が制限される場合
著作財産権は強い権利ですが、日本の著作権法では、文化の発展や公共の利益に配慮し、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる例外規定がいくつか設けられています。例えば、個人的に楽しむための「私的使用」や、他人の著作物を自分の著作物中に取り込む「引用」などがあります。これらは、個人的な目的や公共の利益を考慮した一部利用が許される場合です。
引用の範囲と条件
引用が合法であるためには、出典を明記し、必要最小限の引用に留めることが求められます。
教育や研究における利用
教育や研究の目的であれば、著作物の利用に対して一定の例外が認められることがあります。ただし、著作権者の権利を侵害しない範囲で行うことが必要です。
図書館やアーカイブでの利用
図書館やアーカイブは、著作物の保存や利用に関して特別な例外が設けられていますが、これも著作権法の範囲内で行われる必要があります。
まとめ
本記事では、著作財産権の基本的な概念から、具体的な権利の種類、その取得方法、そして保護期間や権利の制限に至るまで、幅広く解説しました。
著作財産権は、クリエイターの努力と創造性を守り、文化の発展を支える非常に大切な権利です。インターネットが普及し情報が簡単に共有される現代において、この権利を正しく理解し適切に扱うことは、誰もが安心して創作活動を行い、文化を楽しむために不可欠です。
もし、ご自身の作品に関する著作権についてさらに詳しく知りたい場合や、具体的なケースで疑問が生じた場合は、専門家への相談や著作権情報センター(CRIC)などの信頼できる情報源をご活用ください。
著作権ドットコムで「著作権の困った」を解決!
著作権ドットコムでは、今回ご紹介した著作財産権だけでなく、著作権に関するあらゆる疑問や「困った」を解決するための情報を分かりやすくお届けしています。
「この場合はどうなるの?」「こんな時、著作権侵害にならない?」といった具体的な疑問がある方もご安心ください。疑問解決に役立つQ&A記事や、さらに専門的な情報も多数掲載しています。
ぜひ、あなたの創作活動やビジネスを守るために、他の記事も参考にしてみてください。